文鳥はインコの中でも特に卵詰まりと言う病気になりやすいです。

卵詰まりは放置すると極めて短い時間にインコを弱らせ、最悪落鳥させてしまう恐ろしい病気です。
今回は文鳥の卵詰まりの症状と応急処置、予防方法について解説します。
卵詰まりの症状

卵詰まりとは、本来生まれるはずの卵が、卵の異常、親鳥の体調不良や加齢など様々な要因により体外に排出されずに詰まってしまう状態です。
主な症状は以下のものが挙げられます。
- おなかに硬く丸いものがふれる。
- おしりから卵が見えている状態が30分以上続く。
- 元気がなくなる、食欲が低下する。
- うずくまって呼吸が荒くなる。
これらの症状が1つでもみられたら、様子見を絶対にしないですぐに病院に連れて行きましょう。
放置するとどんどん悪化します。
卵が体内で割れ、殻が卵管を傷つけ出血する危険も非常に高いです。
文鳥が卵詰まりになりやすい理由

文鳥のメスの落鳥原因の大多数をしめるのが、この卵詰まりであるといわれています。
文鳥が卵詰まりになりやすい理由は諸説ありますが、「カルシウム不足になりやすい」「他の手乗りインコに比べ嫉妬深く、濃厚なスキンシップを求めるため発情しやすい」といった理由からなのではといわれています。
文鳥の卵詰まりの原因

インコの卵詰まりの原因はいくつかあります。
- カルシウム不足
- 日光浴不足
- 産卵が多い
- 親鳥の年齢や体調。
インコはボレー粉から取り入れたカルシウムを日光浴で生成したビタミンDによって体内に取り入れます。
つまり、折角カルシウムを取り入れても、日光浴不足でビタミンDが生成されないと、吸収されないのです。
カルシウム不足になると、卵の殻がしっかり作られず、やわらかい殻の卵になってしまいます。
その結果、卵がスムーズに排出されずに卵詰まりとなってしまうのです。
加えて、発情などで産卵する機会が多いと、それだけ沢山の卵を体内で作ると、体はカルシウム不足になり、やがて軟卵になってしまうでしょう。
軟卵だけでなく、カルシウムが不足すると、様々な体調不良の原因になってしまいます。
また、親鳥が若過ぎる、歳をとっている、急に寒くなったといった複合要因でも発症します。
飼い主さんの日光浴やボレー粉を与えること対する認識が甘い人が多いのも、卵詰まりの増加の一因です。
文鳥の卵詰まりの応急処置

文鳥は体が小さく、体力もありません。
卵詰まりの発症を発見したら、すぐに病院に連れて行くのが一番の応急処置です。
獣医にすぐにどうしても行けないときは29~30度に保温しましょう。
排出孔にオリーブオイルをぬって産卵を促す方法もありますが、体を冷やすリスクが高く、おすすめできません。
元気であっても、半日もしないうちに症状が悪化していきますので、病院へすぐ行く事が本当に大切です。
文鳥の卵詰まりの予防方法

文鳥の卵詰まりを予防するために効果的な方法が3つあります。
- カルシウムがとれるように意識した生活をする。
- 発情しすぎないようにする。
- 夜遅くまで起こさない(夜は寝かせる)。
文鳥の卵詰まりは一旦発症すると症状の進行が早く、治療が難しいのが現状です。
毎日の生活の中で予防できることをやりましょう。
カルシウムがとれるように意識した生活をする。
週に3~4回、10分~15分の日光浴とボレー粉やビタミンを普段からしっかりとるようにしましょう。
特にシナモン文鳥やシルバー文鳥といった色素の薄い文鳥は、長時間の日光浴で体調を崩すことがあるので、まずは5分の日光浴からはじめましょう。
日光浴中~日光浴後1時間は様子をみて、日光浴の時間を加減するようにしてください。
カルシウムはボレー粉、ビタミンは野菜やフルーツ、ネクトンなどのサプリで補うことが可能です。

発情しすぎないようにする。
人に良く慣れた文鳥は、飼い主を発情対象とみなす場合があります。
飼い主が背中を撫で過ぎると発情してしまうことがありますので、発情し過ぎないように接することが大切です。
また、おもちゃや鏡などにも発情する場合がありますので、そういった発情の対象物は取り除いておいてください。
日照時間を抑える。
インコは日照時間(昼間の明るい時間)が長くなる春や秋に繁殖をする性質があります。
そのため、夜寝かせる時間が遅かったり、夜更かしが多いと、繁殖期と思い込んで発情することがあります。
朝になったら起こし、暗くなったら寝かせる、自然のサイクルにあわせた生活を送るようにしてください。
文鳥の卵詰まりの症状と応急処置、プロが実践する3つの予防法!まとめ
- 卵詰まりは進行が早く、救命が難しい病気です。
- 元気でも短時間で悪化します。様子見は絶対にしてはいけません/strong>
- 普段からカルシウム、ビタミン、運動、日光浴を偏りなく与えましょう。
- 発情の対象や原因を取り除き、日照時間が長くなりすぎないようにしましょう。
文鳥の卵詰まりは体力がない分、進行が早く、治療成績が芳しくないのが現実です。
だからこそ、予防と早期発見につとめてください。
放鳥時おなかのふくらみがないかチェックするように習慣付けましょう。
特に急に寒くなる時期は卵詰まりを起こしやすいので十分に気をつけてください。
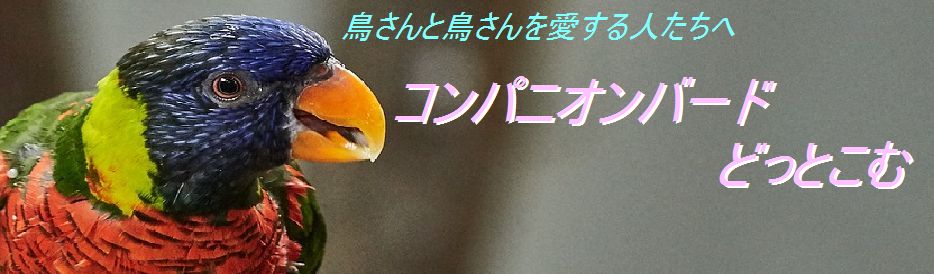
コメント