気温が下がり、保温が難しくなる冬はインコにとって難しい季節です。
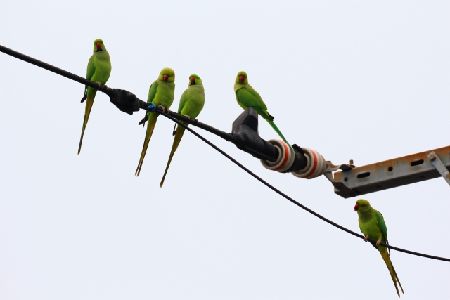
冬場は飼い主さんもよりいっそう健康管理に気をつけていると思います。
特に気をつけてほしい冬に多いインコの病気について5つピックアップしていきます。
冬に多いインコの病気1.風邪

くしゃみや咳を何度も繰り返し、鼻水を出しているようなら風邪を疑いましょう。
急な気温の変化や、夜の保温が不完全な場合が原因で発症することがあります。
インコは風邪を引くと食欲が落ちてしまい、そこからさまざまな体調不良を連鎖的に引き起こしてしまいます。
たかが風邪と人間の風邪の感覚でインコの風邪を放置することは危険です。
保温をしっかりして体を冷やさないようにすることが大切です。
風邪を軽く考えるのは危険!_
人間の感覚では風邪=すぐ治ると思いがちですが、インコの風邪は治りにくく肺炎などの病気に移行しやすいです。
素人判断せずに必ず獣医の診断を受けましょう。
冬に多いインコの病気2.卵詰まり

メスにのみ発症する病気で、体の中で卵が詰まってしまい排泄が一切出来なくなる病気です。
気温が下がり寒くなることでも発症するため、冬に好発します。
落鳥する確率が非常に高く、発覚したら即日病院に連れて行かなければ命の保障はありません!

冬に多いインコの病気3.低体温症

長時間低い気温や冷風に晒されていたことで体温が下がってしまった状態です。
インコや鳥類の体温は41~42度くらいありますので、38度を下回ると低体温症を疑わなければいけません。
見た目が元気で食欲があるようなら、保温することで持ち直すことがありますが、食欲不振、ぐったりしている、寒がっている、体が冷たい状態になっていると回復が困難です。
すぐに病院へ連れて行きましょう!
冬に多いインコの病気4.熱中症

インコを大切にするあまり、過度な保温を行ってしまい室温があがりすぎたために冬でも熱中症を発症する例が毎年報告されています。
闇雲に保温をすればよいわけではありません。
インコの状態をよくみること、換気を適度に行うことで空調を調整してください。
口を開けてパクパクさせている、羽を浮かせているといったしぐさは熱すぎて放熱している状態です。
保温しすぎにならないように注意してください。
冬に多いインコの病気5.シードジャンキー

寒くなると動物は皮下脂肪をためようと脂質の高い餌を食べるようになります。
そのため冬場はひまわりの種や麻の実といった高脂質シードを好む傾向がでてきます。
それが癖づいてしまい、冬場に限らず食べるようになって行き、結果的に肥満や肝臓障害を引き起こすことになります。
このようなことにならない様に、シード食が主食の場合はシードの含有成分の調整を飼い主で行う(特に脂質の高いシードは取り除いたり、増やしたりするなどの調整が大切)必要があります。
インコの病気を未然に防止するには

- 常にインコの様子や状態に気を配ること
- 「いずれ良くなるだろう」と様子見をしないこと
- 保温に常に気をかけること
インコの病気や不調を予防するには、普段の生活でインコの様子がいつもと違わないかのチェックを怠らないことです。
エサの食べっぷり、放鳥時の行動、ケージの中での行動、いつもと違ったことはありませんか?
「エサの減りが悪い」「放鳥中は元気に飛び回っているのに今日はずっと動かない」「ケージの中で寝ていることが多い」といつもと違う違和感があれば原因を調べ病院へ連れて行きましょう。
特にインコは不調を隠す習性があり、飼い主さんに体調が悪いのをバレないようにしようとします。
そのため一見元気を装っていることが多いので、「いつもと違うけれど様子見で大丈夫だろう」という判断は危険な場合があります。
不調を隠す習性があるにも関わらず、目に見えて具合が悪そうなときは、不調を隠せないほど進行していると考えるべきです。
すぐに病院へ連れて行き、適切な処置と診察を受けるようにしてください。
また、インコは保温をすることで体調が持ち直すことが多い動物です。
調子が悪いと思ったらまず保温する習慣をつけましょう。
冬に多いインコの病気5選!症状と対処法。まとめ
- 冬に多く発症するインコの病気がいくつかあります。
- とくに「卵詰まり」は落鳥率が非常に高いため迅速な対応が必須です。
- 保温は愛鳥の様子や室温に気を配って行ってください。
いかがでしたでしょうか。
たかが風邪、ちょっと冷えただけと思うかもしれません。
しかしインコにとっては命をおとすかもしれない重大な病気の症状であることが多いのです。
人間の感覚で判断しては大変危険です。
違和感を感じたら元気なうちに病院に連れて行き、早めに対処することが愛鳥の命を守ることにつながります。
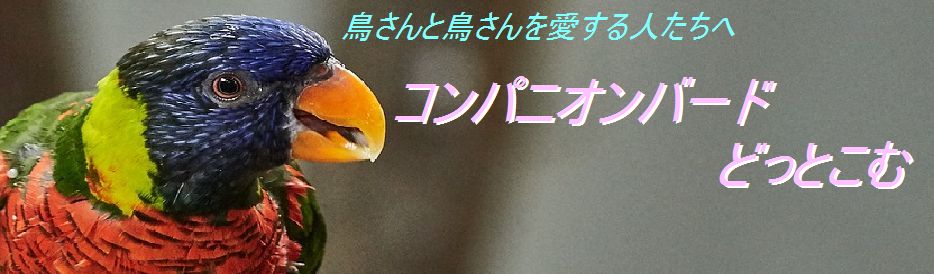
コメント